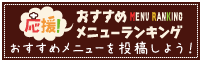a24films.com
ルドルフ・ヘスについて、幾ばくかの知識はあった。本作「関心領域」は注意深くナチスの極悪人という典型を避けて描いているという点では、これまでの映像表現とは一線を画している。
あの時代のあの場所を今、いかにして伝えるかという方法論が念入り且つ繊細に描かれて行く。
スピルバーグが「シンドラーのリスト」('93)であの時代をモノクロで描くことでドキュメンタリー的効果を狙っていたが、それは「観る側の映画的記憶」に頼った表現でもあった。殆どの観客が色のついた「かの時代の映像」を観てはいない。色彩は、生存する犠牲者と加害者(傍観者も含む)の記憶の中にだけある筈だ。
本作はまずその点を抉って来る。
まるでモノクロに着色したかのようなルック、だがフィルムの質感とは違う、明らかにデジタルの生々しさ。何千本と作られてきたであろうあの時代を描く映画の中で、際立ってリアルに「見える」そして「感じる」。
そう、作り手も観客のその殆ども知らない筈の時代の色を不穏極まりない音の表現とを複合させ、視覚聴覚に訴える禍々しさは新しい体験と言える。
ルドルフ・ヘス(クリスティアン・フリーデル)の妻ヘートヴィヒ(ザンドラ・ヒューラー)の母親の台詞、母親は戦前はユダヤ人家庭の家政婦だった、そして元の雇い主は「塀の向こう」にいると。それが当然であるとも言いたげな言い回しに慄然とする。
当時のドイツ軍勢の中でも親衛隊は非エリート集団だった事がその一言で伝わる。
しかしこのヘスの義母はある日何も告げずに屋敷を出る。母の置き手紙を暖炉に放り込む娘。手紙の内容は観客には示されない。音と匂いに我慢ができなかった事を実の娘に直接伝えられなかったというあの時代の人間関係。
一方状況を全て「是」として、ユダヤ人下女には悪様に「灰にしてやる」と告げるヘートヴィヒ。
一旦はアウシュビッツから離任しながら、ハンガリーからの更なるユダヤ人大量移送の為復帰を命じられるヘス、老婆の連れている犬を愛で、健康診断を受け、妻に単身赴任が終わることを伝え、パーティに出た後、会場の階段で嘔吐する。
この嘔吐で、ハッとなる。ヘスと「我々」に如何なる差があるというのか。犬以外には家族にも笑顔を見せないヘスの感情を押し殺した内心は果たして悪魔と言えるのか。同じく、ヘスの義母は現代でもそこいら中にいるのではないか。
強制労働させられるユダヤ人の為に深夜密かに林檎や梨を配る少女。ネガ反転のようなルックで描かれるそれは、「私たち」の中の誰か、である筈だが決して私ではない事を撃つ。
この映画のモチーフは「あなたはその立場になった時、彼や彼女と何が違いますか」という、痛烈な問いに思えてならない。
戦後処刑されたヘス、彼以外の家族は一体どうなったのだろうかと検索してみると、2015年のこんな記事を見つけた。
blog.goo.ne.jp
平日昼間の大阪、ほぼ満席。まだ佳き映画の力は信じられる。
佳作、お勧め。







![日本殉情伝 おかしなふたり ものくるほしきひとびとの群 デラックス版 [DVD] 日本殉情伝 おかしなふたり ものくるほしきひとびとの群 デラックス版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51cCbPssbOL._SL500_.jpg)